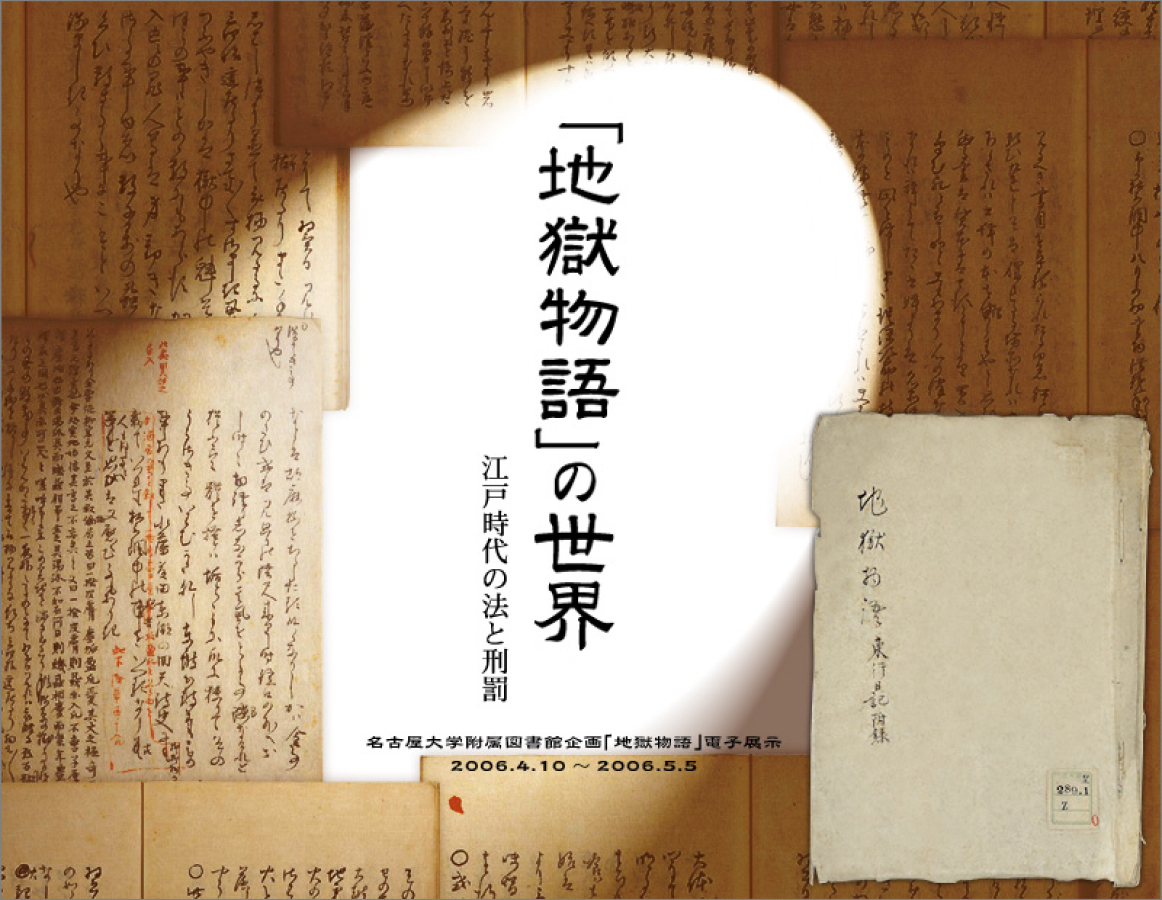電子コレクション
「地獄物語」の世界 -江戸時代の法と刑罰
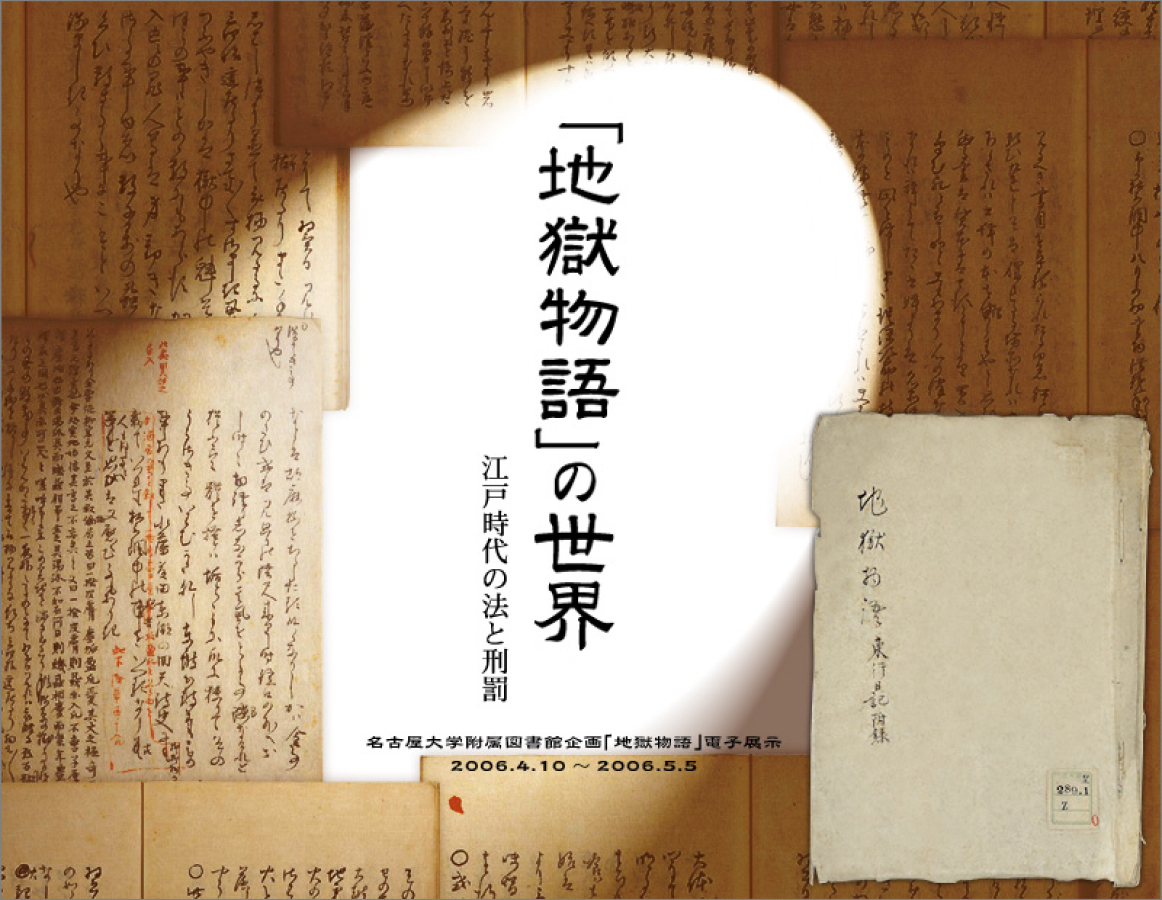
江戸時代の獄中生活を知る「地獄物語」の世界へようこそ
『地獄物語』は安政の大獄に関係して「青山の獄」のち「浅草の獄」に禁錮された著者『世古恪太郎』が、獄中生活の見聞や、同囚や牢番より聞いた珍談奇談を書き綴った雑記随筆。蘭医森川鞏斎より厚遇を受けたこと、浅草の卜者山口千枝の話、夥しい虱の話、材木屋須原屋角兵衛(書林須原屋茂兵衛の一統)の手代長七の豪遊譚、獄中の読書、勝麟太郎の話、同囚の修験の語る江戸に於ける卜者の上手のこと(第一に根岸の青雲堂、但し故人、第二に浅草の山口千枝、第三に芝神明前の白龍子、但し親の赤龍子よりも劣る)、二条左府公の公達寛斎(三条前内府の猶子)のこと、火事の際の獄の「開ケ放し」のこと、浅草の獄中で将棋の名手(実は宗桂の子)と将棋を指した話(著者はかつて浪華で平塚瓢斎と将棋を指したことあり)、獄の魁(牢名主)と亜魁より古今三鳥と諫鼓鶏について問われた話等、面白おかしく描かれた手記です。
※
なお、地獄物語の詳しい解説や世古延世の関係資料については、 展示図録 をご覧下さい。 (名古屋大学附属図書館HP「催事」からダウンロードできます)
「地獄物語」の著者 世古恪太郎を知る
世古恪太郎延世(せこかくたろうのぶつぐ)(1824-1876)略伝
 松戸市図書館郷土資料室提供
松戸市図書館郷土資料室提供
江戸後期の勤王家。文政7年(1824)、松坂西町の富豪黒部屋に生まれる。足代弘訓や斎藤拙堂に学び、弘化2年(1845)には上京して三条実万に面会。以後しばしば公家や諸国志士と交わるが、安政大獄で江戸送りとなり、病囚を入れる浅草の溜で想像を絶する「地獄」を体験した。その後、文久2年(1862)、三条実美に召され再び国事に奔走。宮内権大丞に任ぜられ、古社寺の保存法を立案する。明治9年(1876)東京で病没、享年53。青山墓地に葬る。著作に、尊攘派列伝たる『唱義聞見録』、捕縛寸前までを記録した『銘肝録』、捕縛・入牢体験を綴った『地獄物語』『東行日記』などがある。
「地獄物語」の書かれた 時代背景(安政の大獄)
アヘン戦争(1842年)以来の深刻な対外関係を背景に、幕府は朝廷との結合強化を図り、政治的権威を保持しようとする。 しかし、政治能力のない将軍家定の継嗣問題が浮上するなか、幕府がアメリカの要求する不平等条約締結へ向かうのをみて、松平慶永ら有志大名、尊攘派の志士・草莽(そうもう)らは、朝廷への働きかけ(京都手入)に奔走するようになる。 紀州藩用達の富商世古恪太郎もその一人で、三条家に出入りし、水戸藩への降勅事件などにも関与している。こうした動きに対し、安政5年(1858)4月、譜代筆頭の井伊直弼が大老に就任し、条約締結を強行するとともに反対派への徹底した弾圧を開始する(安政の大獄)。 それは、死罪となった橋本左内、頼三樹三郎、吉田松陰らをはじめ、多数の大名、幕臣、志士を厳罰に処すことで威信回復を図ろうとするものであったが、これに激した水戸浪士により井伊大老が暗殺され(桜田門外の変)、幕府の権威は急速に衰えていったのである。